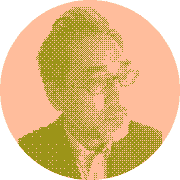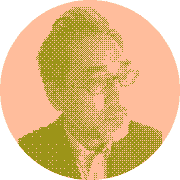佐々木正人/生態心理学に関するノート
[著作] レイアウトの法則―アートとアフォーダンス
- (2003, 春秋社, ブックデザイン:鈴木一誌+武井貴行) →amazon
- 本ページ内では以下「レイアウト」と略す
目次
- [序]
- [1:レイアウトの法則]
- [2:光のレイアウト]
- 「正確に言えば光は見ることができない―絵画とジェームス・ギブソンの視覚論」
- 「光の経験―デッサン派 vs. 色彩派」(松浦寿夫・高島直之との鼎談)
- 「包まれる―写真と視覚」(畠山直哉との対談)
- [3:余白のレイアウト]
- 「小屋の力、街の愉しみ」(塚本由晴との対談)
- 「ページとフォーマットの劇場」(鈴木一誌との対談)
- [4:力のレイアウト]
- 「相撲と無知」
- 「リハビリテーション―制御・入れ子・協調のデザイン」
- 「生へといたる消滅―ウイリアム・フォーサイスの動き」
- [結]
- 「レイアウトのレイアウト」
- 「肌理[キメ]と粒[ツブ]」
[著作] ダーウィン的方法―運動からアフォーダンスへ
- (2005, 岩波書店) →amazon
- 本ページ内では以下「ダーウィン的」と略す
- 佐々木さんの運動論を集めた本
- これはいい本だなー。一冊の本へのまとめ方、集められたテキストのヴァラエティとそれらを繋ぐモノ。ダーウィンの「ミミズと土」を細かく読み解いていき、ダーウィンが〈何に触れようとしていたのか〉に迫りそれをすくいだそうとするそのプロセス。エドワード・S. リードへの追悼文ともなっているテキストは、もちろんリードの仕事の紹介となっているわけだが、佐々木さん自身がどのような思い(うーんこの言葉ではしっくりこないが)を持って自身の研究をやっているのかも伝わってくる。これは前から思っていたことだが、佐々木さんは「単なる学者」という感じがしない人である。
[著作] 知覚はおわらない―アフォーダンスへの招待
- (2000, 青土社, 装幀:戸田ツトム) →amazon
- 本ページ内では以下「おわらない」と略す
目次
- [1:アフォーダンス入門]
- 「リアリズムのお稽古」
- 「アフォーダンスの心理学」
- 「スポーツの究極にある緩慢さについて―澤野雅樹との対話」
- 「想起の「自然」についての覚書」
- [2:表現]
- 「表現と同時性―寺山祐策と武蔵野美術大学視覚デザイン室の学生たちの対話」
- 「光に触れる意識―ジェームズ・タレルに聞く」
- 「マイクロスリップと演技―平田オリザとの対話」
- [3:運動]
- 「知覚はおわらない」
- 「義足の生―歩行という意識、義肢装具士・井ノ瀬秀行に聞く」
- 「いちど起こること」
文献メモ
- 本多啓・三嶋寛之との鼎談「拡張するアフォーダンス」 『UP』 2005年8月号
- 深澤直人についてのテキスト「意識の中心をプロダクト化する」 『広告批評』 2005年6月号 特集=深澤直人の仕事
- 『思想』 2005年2月号 特集=知覚の謎 冒頭に収められた佐々木さんのテキストは短いものでこちらに全文が載っている。他に村田純一・信原幸弘・染谷昌義のテキストを読むことができる。
- 村田純一・無藤隆との鼎談「ソウルからマインドへ―アンダーグラウンド心理学の構想」 『現代思想』 2000年4月号 特集=心理学への招待
- 後藤武・佐々木正人・深澤直人 『デザインの生態学―新しいデザインの教科書』(2000, 東京書籍)
- 佐々木正人・三嶋博之【編訳】『アフォーダンスの構想―知覚研究の生態心理学的デザイン』(2001, 東京大学出版会) 「生態心理学の最新・最先端を並べた、国際的なレヴェルでの生態心理学の動向を知るにふさわしい本」(「拡張するアフォーダンス」での佐々木さんの発言より)
- 佐々木正人・三嶋博之【編訳】『生態心理学の構想―アフォーダンスのルーツと尖端』(2005, 東京大学出版会) 「ルーツを歴史的にたどる、生態心理学の思考の起源にまでさかのぼる論文と、それが現在どのような主張として開花しているのか、そういう刺激的な内容を集めた本」(「拡張するアフォーダンス」での佐々木さんの発言より)
***
- 学問的に(学者として)どうかは分からない・知らないが、佐々木正人という人は魅力があるように思う
著作からのメモ(未整理)
- 「リードによれば、20世紀後半の世界をおおっているのは「不確かさへの恐怖」である。あいまいな感覚にしたがう「思考しない身体」を、「思考するマインド」に結びつけることが近代以降の人々が考えた「確実さ」であるが、二つが混在している限りは「不確かさ」が残るのだとする、デカルト由来の発想が人々にひろがっている。「思考するオフィス」(精神労働)と「思考しない工場現場」(肉体労働)という架空の分離、労働者を道具を調整する人から、機械の流れを維持する「装置」に変化させた仕事の細分化、「確実で速いこと」を最上位の価値とする仕事の「ファストフード」化、選択すべきことが最初から決まっている環境の「メニュー」化があらゆるところで進んでいる、「現代の仕事場では経験が衰退」しているのである。」(「エドワード・S・リードの仕事」, ダーウィン的, p.78) この部分だけの引用だとちょっと「分かりやすすぎる」感じかな。佐々木さん曰く、リードの著作には「どこをとっても薄くも、単線的でもない。わかりにくい魅力に満ちている」(「ソウルの心理学者」, ダーウィン的, p.134)という
- 運動
- 「たしかに在ること」「自然に、どこにでもある「運動」から、もう一度、心理学をはじめたい」(ダーウィン的, p.8)
- 「「運動」ならば、どの「運動」も、一回限りのことであるということ、つまり「運動」というものが本質的にユニークだということ」」(ダーウィン的, p.14)
- 「アフォーダンスの概念には、価値や意味が環境中に実在しているという主張が含まれている」「アフォーダンスは、個々の動物との関係において規定される個別的・特殊的な特性であるが、それでもそれは環境の側の実在する特性であり、主観的な価値や意味ではない」(河野哲也『環境に拡がる心』 p.14, 強調は原文では傍点)
- ジェームス・ギブソン
- ギブソンの「像に基礎を置く視覚論を否定し、新たな視覚論を構築しようとする」試み
- 包囲光
- 「媒質中のあらゆる点を取り囲む光」「包囲光には周囲の表面のレイアウトという「情報」が内在している」
- 「媒質に浮遊している塵や表面にある微細なキメによって、光源からきた放射光は散乱し、多重の反射あるいは残響を引き起こしている。このように光があらゆる方向から媒質中を交差し、そこを満たしている状態を照明という。照明された媒質中では、すべての場所がすべての方向からの光によって包囲されている。このような光の状態を包囲光という。包囲光にはその周辺のレイアウトがその構造を保って投射されている。」(「アフォーダンスの心理学」, おわらない, p.30)
- 「見ることは媒質中にいて、そこにある光の構造に持続して接触し、構造の詳細に気づくことができるようになることである。視覚のために光にある情報は、脳で構成されなくとも、環境の中に在る。視覚はそれを捕獲する活動のことである」(レイアウト, p.51-p.52)
- 「……ギブソンは、動物の視覚が眼球の解剖学的な構造ではなく、動物周囲の地球環境が与えていることによって可能になるというきわめてオリジナルな理論を公表した。西欧の哲学者が長く難問としてきた二次元の網膜像からなぜ奥行のある三次元世界が見えるのか、という問題に、それはどの環境表面にも微細な肌理[きめ]があり、それが動物を包囲している光に投影されているからだとギブソンは答えた。周囲に何があるかを知ろうとしない哲学者は、意味の根拠を動物器官の方だけに求めてきた。しかし周囲に広がる肌理の勾配やその変形を投影した光には、環境がどのような意味を持っているかを示す豊富な情報が含まれている。知覚は動物身体の精妙な動きが達成することでありながらも、環境からもたらされることである。」(ダーウィン的, p.17)
- 遮蔽
- 「ある表面が背景にある他の表面を覆い隠すようにして観察者に近づいてくるとする。そのとき包囲光に起こっているのは、向かってくる表面の光の輝きが背景となっている表面の輝きと置き変わることである。この場合、包囲光場の輝きには、中心から周辺に拡大するように徐々にある輝きが添加していく。添加の先端部を「遮蔽縁」とよぶ。」(「アフォーダンスの心理学」, おわらない, p.31)
- 包摂(・されている)
- 続いていく、持続
- 隣り合う・
- 境界、縁[へり]=表面の接合するところ
- レイアウト
- 固さのレイアウト
- 「僕がレイアウトというのはこの情報の複合のことです」「知覚は点や線ではなくレイアウトに生ずる」(「リハビリテーション」, レイアウト, p.219)
- 肌理(テクスチャー)
- 表面(サーフェス)
- 「肌理に満ちたサーフェス(表面)」、「多種の表面が動物を取り囲んでい」る
- 知覚
- 知覚システム:「ギブソンは幾つもの感覚器が複合して、周囲を探索する協調のシステムが身体に成立していると考えて、それを知覚システムとよびました。単一の感覚受容細胞ではなく、それらをも含んだ組織が身体にはあり、それが環境の意味を探していると述べた」(「リハビリテーション」, レイアウト, p.216)
- 情報
- ギブソンの概念「情報」:「ギブソンは知覚システムは周囲のエネルギー流動のマクロンな構造と循環しているとしました。周囲のエネルギー場のこのレベルをギブソンは「刺激」に対して「情報」と呼びました。情報としてギブソンが最初に発見したのは、地面のような環境表面の肌理(テクスチャー)です」(同前, p.216)
- 知覚システムは、そのような「情報」を利用している(「情報」に協調している)、そのような「情報」(が見出されること?)によって知覚が行われる、そのような「情報」は動物が動くことによって「作り出」される、「動くと現れることが周囲を知ることの資源になっているわけです。移動イコール情報。移動と知覚は同じこと」(同前, p.218)
- 意味の知覚
- 「……変形が複合する変形を私たちは出来事とよんでいる。私たちは出来事に意味を知覚する。出来事とは複合するレイアウトの変形のことであり、意味はたいがいは二つ以上の変形の比に知覚される。/周囲には出来事があり、それが動物を包囲している。」(レイアウト, p30)
- 行為
- 姿勢
- 「動物の運動はいかなる時にも重力を免れられない。重力に抗することで、あるいは従うことで動きに姿ができる。重力に相対する動物運動の性質を「姿勢」とよぶが、植物にも姿勢がある。植物の運動も重力が地上にもたらしている上下軸に貫かれている。」(レイアウト, p.18)
- 「秩序を獲得した動物の揺れのことを私たちは定位、あるいは姿勢とよぶ。寝ている動物にも起きている動物にも姿勢があり、彼は定位している。動物が定位するのは、自ら動く動物が周囲とは異なる独自の揺れであり、その揺れが常に周囲の揺れとの折り合いを探り続けているからである。生きている場合この姿勢が崩れることはあまりない。」(レイアウト, p.33)
- エドワード・S・リードの概念としての「姿勢」、動物運動の単位としての「姿勢」:「姿勢は旧来の「姿勢」の読み替えではない。伝統的運動研究は「姿勢」を「自動化した、重力に抗する伸張反射の総和」と定義してきた。しかし姿勢は重力という唯一の力への応答ではない。いま私は椅子に腰掛けてキーボードを叩いている。身体は両足が着いている床だけではなく、椅子の背、椅子の座面、手首が触れている机の端、手掌が置かれているキーボードの端など、身体各部に対し反作用力を与える力の場に同時に置かれている。このような多方面から全身に及ぶ力は常にある。もちろん移動する場合には加速度もそこに加わる。結局、姿勢は多数の競合する場で刻々と組織化されることになる。」(「ソウルの心理学者」, ダーウィン的, p.128) /「姿勢は静止ではなく持続である。姿勢はそのまま運動と連続している。動物運動の基本ユニットである姿勢は、運動でもある。」(「いちど起こること」, おわらない, p.277)/「動物の運動は姿勢の隣接である。」(同前, p.278)/「リードは「運動とは一つの姿勢を他の姿勢へ機能的に入れ子すること」でもあると定義した。「入れ子」とは互いに包摂する、区切りのない要素間の関係である」(同前)
- 不変(・項)
- 変形するものと、「変化の基礎にある」「不変なシェープ(姿)」(「リハビリテーション」, レイアウト, p.218)
- 一つの運動は複数の運動間の関係である
- 「運動は二つの動きからなる。それは二つ以上の時間の重なりである。そして二つ以上の姿勢の入れ子である。」(「いちど起こること」, おわらない, p.279)
- 複数の運動が組織され一つの行為となる
- 協調(・システム)
- ベルンシュタインの用語「協調」:「身体の動き間の関係」(「いちど起こること」, おわらない, p.264)
- ベルンシュタイン問題:「一言でいえば、制御に関するすべての責任を、どこかに仮定された中枢にまかせてしまわずに、動物の運動について説明することはできるのか、できるとしたらどのようにすれば可能なのか、という問い。半世紀も前に、ロシアの生理学者ニコライ・ベルンシュタインが提起した」(おわらない, p.256)/「身体の解剖学的な個の部分に起こる変化を基礎にして身体の動き方をモデル化しようとする試みは、「個」があまりにも多くて、膨大なそれらが一挙に縮減してできるマクロな動きを説明する方法を見いだせなかった。それが「ベルンシュタイン問題」である。」(「いちど起こること」, おわらない, p.265-266)
- ベルンシュタインが用意したいくつかの解答。一つは、「運動を環境と一つのものととらえる考え方」。第二に「運動に起こる変化、つまりその発達が、運動を構成している、より「小規模の運動」間の関係によって生じてくるとする考え方」(同前, p.256-257)
- 「われわれの全身運動を記述しようとしたら、じつに多くの変数からなる非線形微分方程式を導かなければならない。そこでの独立な変数の数のことを自由度と呼ぶ。仮に、すべての変数がランダムに動いているとすれば、運動の自由度はその変数の数に等しい。ところが、いくつかの変数がそろって運動すれば、自由度は減少する。われわれが日常的に行う運動には、ある種の秩序があるから、運動が生じるということは、自由度を減少させることにほかならない。運動制御の問題に関してこのように現代的な考察を初めて行ったのは、ベルンシュタイン(Bernstein, 1966)である。彼は、パブロフの反射理論が主流だった時代に、運動制御の本質は自由度問題であると主張した。」(多賀厳太郎 『脳と身体の動的デザイン―運動・知覚の非線形力学と発達』, 2002 p.92) 「Bernstein, 1966」として参照されているのは『The co-ordination and regulation of movements』(Pergamon Press)
- (ロッドニー・ブルックスの「クリーチャー」について)「計算とか表象とか記憶などの旧来の知能の原理ではなく、非常にシンプルな感覚-運動を重層化する原理で知能の原型を設計できるというのでみな驚かされたわけです。」(「リハビリテーション」, レイアウト, p.214) ※ブルックスについて主題的に扱われてはいない。エドウィン・ホルトの「架空の水棲動物」についての話の中に出てくる部分
- 「感覚-運動がリンクするところに周囲への意識が生ずる。そこに心が現れるということです。エドウィン・ホルトは心の起源は運動の複合であると考えた」(同前 p.215) 物の登場する心理学の構想
- 「人の棲まうところの周囲の表面は変形されて、森にはないレイアウトになっている。土木、化粧、料理は表面のレイアウトの変形である。この変形では加工されても元の表面の意味が残る。いくら化粧してもその顔はその顔であり、いかように切断されても魚は魚である。もし化粧が加工前の顔の表面の意味を変えてしまったらそれは化粧ではなく顔は仮面になる。もしコックがニンジンでトマトの味を出したら、それは料理ではなく、コックはマジシャンになる。/土木、化粧、料理は、周囲の表面に意味を探し当てることのできた人が、その意味を他の人に示したいと、表面にほどこした強調である。……」(レイアウト, p.36-37)
- 「……画面にあるのは線や点ではなく情報である。画家は猫の形とともに、猫の変形を描いている。つまり猫の不変、猫の情報を描いている。絵画を見ることは像を解釈することではなく、画家が発見して、表現しようとした不変情報を、鑑賞者が画面に探すことである。」(レイアウト, p.53-54)
- 「さて、ここまでに述べた「運動」の二つの性質、それから帰結するすべての「運動」のユニークさの肯定は、もしかすると読者を鼓舞するのではなく、不安をもたらすのかもしれない。決定などはない、決定はどこまでも遅延されている。動きは毎回異なる。どの一階もユニークである、と言うことは、じつは「運動」について何も言っていないに等しいのではないか、と。どの領域でも確実なことなどないという勇ましい主張があり、それを好む一群の人々がいるものだが、「運動」の領域でも事情は同じだったのか、という嘆息が聞こえてきそうである。/しかし、何もかもを相対の水面の下に沈めてしまえるほど、事実は脆弱ではない。事実とはそのように物語られることの先にある、わかりにくさのことでもある。」(「運動と環境へのプロローグ」, ダーウィン的, p.15)
- 「何かを語るときにいつも背景をなす「理論」があって、結局、議論がそこに収斂していくということはどの領域でもよくあることだ。心理学の領域でもいつもそのように行われてきた。つまり「発達そのもの」ではなくて、発達をどのようなことと考えるのかということの方に関心の中心があった。現在でも「古いグランドセオリー」に代わる、「次の理論」を模索している人はたくさんいる。しかし一九九〇年頃のわが国ではそのような「理論を中心にする方法が少し緩み始めていた、と筆者は感じたわけである。」(「発達すること」, ダーウィン的, p.137)
- 佐々木さんは対談の人でもあるよな
- 竹内敏晴、佐伯胖、鈴木一誌、松浦寿夫、高島直之、畠山直哉、塚本由晴、ジェームス・タレル、平田オリザ、深澤直人、河本英夫
|